カードローンの返済を延滞してしまうと、どのような影響があるのでしょうか。「少しくらい遅れても大丈夫」と軽く考えている方もいるかもしれませんが、実は延滞には深刻なリスクが伴います。
本記事では、カードローンを延滞した場合の具体的な影響から、延滞を避けるための対処法、既に延滞してしまった場合の対応策まで詳しく解説します。
カードローンを延滞するとどうなる?段階別リスク解説

カードローンの延滞は、時間の経過とともにリスクが段階的に増大していきます。どのタイミングで何が起こるのか、具体的に見ていきましょう。
延滞1日目〜数日:遅延損害金の発生
返済期日を1日でも過ぎると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は年率20.0%程度に設定されている場合が多く、通常の利息よりも高い金利が適用されます。例えば、50万円を延滞した場合、1日あたり約274円の遅延損害金が加算される計算になります。
「たった数日なら」と思いがちですが、延滞期間が長引くほど返済総額は確実に増えていくため、早急な対応が必要です。
延滞1週間〜1ヶ月:督促連絡の開始
延滞が1週間程度続くと、金融機関から督促の連絡が始まります。
最初は電話やSMSでの連絡が中心ですが、連絡が取れない場合は書面での督促状が送付されることもあります。この段階では、まだ返済の意思を示すことで柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
延滞2〜3ヶ月:信用情報機関への登録
延滞が2〜3ヶ月続くと、信用情報機関に延滞情報が登録されます。
これが俗に言う「ブラックリスト」の状態です。信用情報に延滞記録が残ると、以下のような影響が生じます:
- 新たなローンの審査に通らない
- クレジットカードの作成・更新ができない
- 住宅ローンや自動車ローンの利用が困難になる
延滞3ヶ月以上:一括返済請求・法的措置
延滞が3ヶ月以上に及ぶと、残債の一括返済を求められる可能性が高くなります。
さらに状況が改善されない場合は、以下のような法的措置が取られることもあります:
- 債権回収会社への委託
- 裁判所への訴訟提起
- 給与や財産の差し押さえ
延滞が与える具体的な影響とは
カードローンの延滞は、単に返済が遅れるだけでなく、生活全般に大きな影響を与えます。
遅延損害金による返済額の増加
前述の通り、延滞すると高い遅延損害金が発生します。
例えば、100万円の借入を30日間延滞した場合:
- 遅延損害金:約16,400円(年率20.0%で計算)
- 通常利息:約12,300円(年率15.0%で計算)
このように、延滞により約4,100円も余分に支払うことになります。
信用情報への悪影響(ブラックリスト)
信用情報への登録は、その後の金融取引に長期間影響します。
延滞解消後も、信用情報機関によって異なりますが、5年程度は記録が残り続けるのが一般的です。この期間中は、以下のようなサービスの利用が困難になります:
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- クレジットカード
- 分割払いでの商品購入
他のローンやクレジットカードへの影響
延滞情報は信用情報機関を通じて他の金融機関にも共有されるため、現在利用中の他のサービスにも影響が及ぶ可能性があります。
クレジットカードの利用停止や、他のローンの金利引き上げなどが行われる場合もあります。
カードローン延滞を避けるための対処法
返済が困難になりそうな場合は、延滞する前に以下の対処法を検討しましょう。
返済が厳しい時の事前相談
最も重要なのは、返済が困難になりそうな時点で金融機関に相談することです。
多くの金融機関では、利用者の状況に応じて以下のような対応を行っています:
- 返済期日の延長
- 一時的な返済額の減額
- 利息のみの支払いへの変更
事前に相談することで、延滞を回避できる可能性が高くなります。
返済計画の見直し・リスケジュール
収入の変化や支出の増加により返済が困難になった場合は、返済計画の見直しを依頼しましょう。
リスケジュール(返済条件の変更)により、月々の返済額を減らして返済期間を延長することで、無理のない返済計画に変更できる場合があります。
おまとめローンの検討
複数のカードローンを利用している場合は、おまとめローンの活用を検討してみましょう。
複数の借入を一本化することで:
- 月々の返済額を減らせる
- 金利を下げられる可能性がある
- 返済管理が簡単になる
などのメリットがあります。
既に延滞してしまった場合の対応策
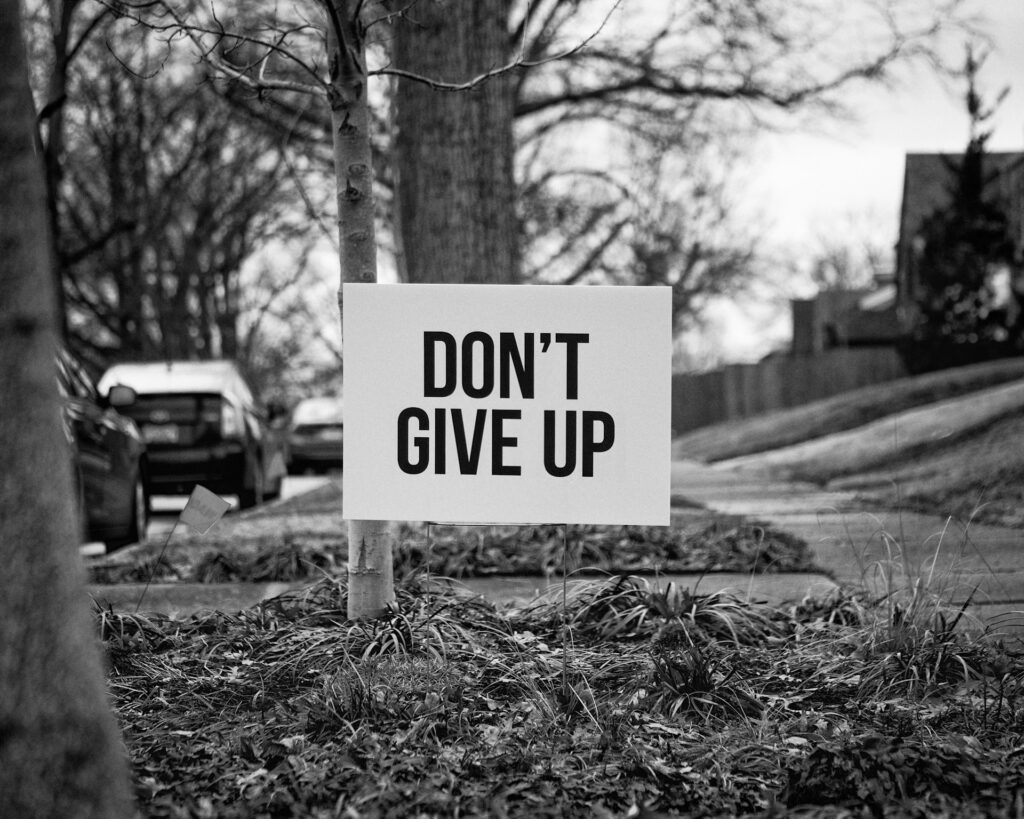
既に延滞してしまった場合でも、適切な対応により状況を改善できる可能性があります。
すぐに金融機関に連絡する
延滞してしまった場合は、できるだけ早く金融機関に連絡しましょう。
連絡時には以下の点を伝えることが重要です:
- 延滞の理由
- 返済の意思があること
- いつまでに返済できるかの見通し
誠意ある対応により、金融機関側も柔軟な対応をしてくれる可能性があります。
分割払いの相談
一括での返済が困難な場合は、分割払いでの返済を相談してみましょう。
延滞分を複数回に分けて返済することで、一時的な負担を軽減できる場合があります。
債務整理の検討
返済の見通しが立たない場合は、債務整理という選択肢もあります。
債務整理には以下のような種類があります:
- 任意整理:利息の減免や返済期間の延長
- 個人再生:借金の大幅な減額
- 自己破産:借金の免責
ただし、債務整理にはデメリットも伴うため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
カードローン延滞に関するよくある質問
Q1. 1日でも遅れたら信用情報に影響する?
A. 1日の延滞ですぐに信用情報に登録されることは一般的にありません。
ただし、遅延損害金は発生するため、できるだけ早い返済を心がけましょう。信用情報への登録は通常、2〜3ヶ月程度の延滞が続いた場合に行われます。
Q2. 延滞したらいつまでに返済すれば大丈夫?
A. 明確な期限はありませんが、できるだけ早い返済が重要です。
延滞期間が長くなるほどリスクが高まるため、遅くとも1ヶ月以内の返済を目指しましょう。困難な場合は金融機関に相談することが大切です。
Q3. 延滞記録はいつまで残る?
A. 延滞解消後、一般的に5年程度記録が残ります。
信用情報機関によって期間は異なりますが、CIC(株式会社シー・アイ・シー)では延滞解消から5年間記録が保持されます。
まとめ:早めの対応で深刻な事態を回避しよう
カードローンの延滞は、遅延損害金の発生から信用情報への悪影響、最終的には法的措置まで、段階的に深刻な問題に発展していきます。
最も重要なのは、返済が困難になりそうな時点で早めに行動することです。事前の相談や返済計画の見直しにより、延滞を回避できる可能性が高くなります。
既に延滞してしまった場合でも、誠意ある対応と適切な相談により、状況を改善できる場合があります。一人で悩まず、まずは金融機関や専門家に相談することから始めましょう。
カードローンは便利な金融サービスですが、計画的な利用と適切な返済管理が何より大切です。困った時は早めの相談を心がけ、健全な金融生活を維持していきましょう。
